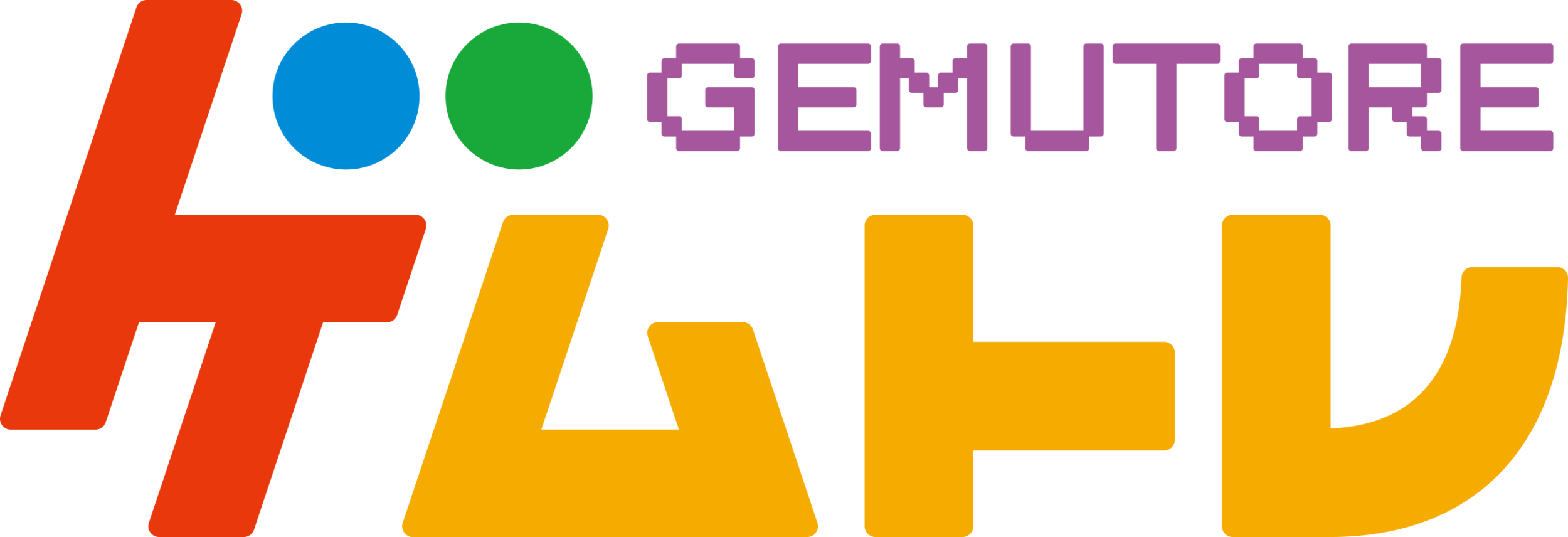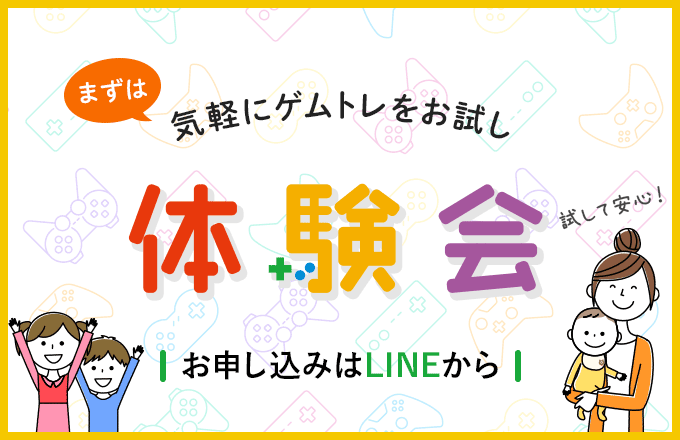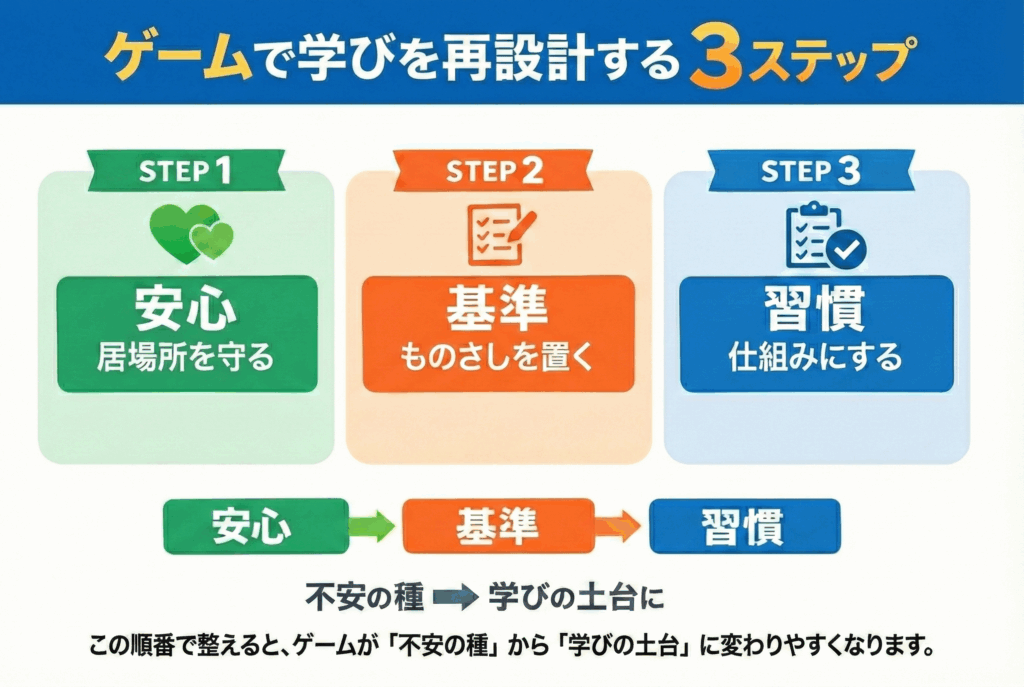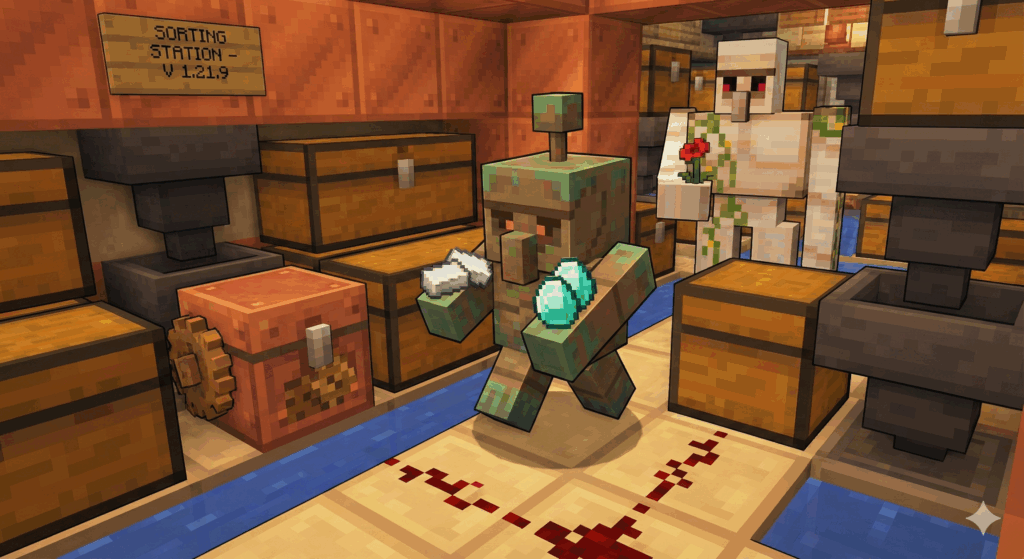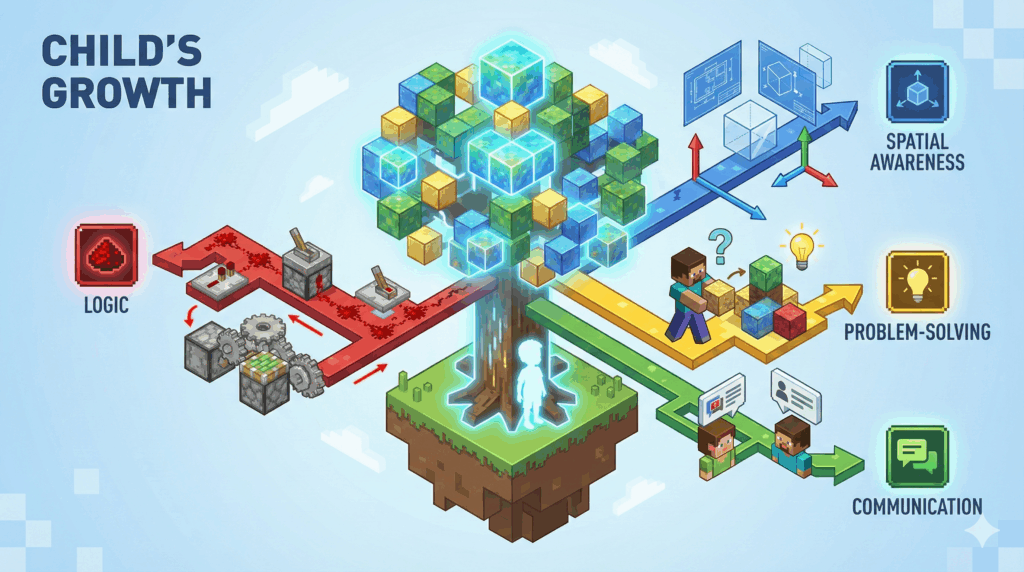不登校は「親のせい」ではありません。お子さんのSOSに悩む保護者の方へ、今知ってほしいこと
お子さんが学校に行けなくなり、「私の育て方が悪かったのかもしれない」「あの時の言葉が原因かも…」と、ご自身を責める日々を過ごされていませんか。
しかし、まず知っていただきたいのは、不登校は決して「親のせい」ではないということです。
現在、不登校のお子さんの数は過去最多となり、決して「特別なこと」ではなくなっています。その背景には、学校や友人関係、ご本人の特性、そして社会の変化など、目には見えない様々な要因が複雑に絡み合っています。
それは、大人が仕事のプレッシャーや人間関係の疲れで休息が必要になるのと同じ、お子さんからの「エネルギー切れ」のサインであり、大切なSOSなのです。
この記事では、保護者の方が「自分のせいだ」というお気持ちを少しでも手放し、お子さんのために「今できること」につながるかもしれないヒントになればと思い書きました。

目次
「私の育て方が悪かった…?」不登校でお子さんを責める前に、まず保護者の方へ伝えたいこと
あなただけではありません。多くの保護者が「自分のせいだ」と悩んでいます
お子さんが学校に行けなくなると、「私の育て方が悪かったのかもしれない」「あの時の対応が間違っていたのでは…」と、ご自身を責めてしまう保護者の方は、本当にたくさんいらっしゃいます。大切なお子さんのことだからこそ、深く悩み、ご自身のせいではないかと苦しくなってしまうお気持ちは、とても自然なことです。
結論:不登校は、決して特定の誰か一人の「せい」ではありません
でも、まず一番にお伝えしたい大切なことがあります。それは、「不登校は、決して特定の誰か一人の『せい』で起こるものではない」ということです。あなただけでなく、誰か敵のような人のせいで起きるものでもありません。
学校での人間関係、勉強のこと、ご本人の心や体の状態、ご家庭でのちょっとした変化など、本当にいろいろな要因が複雑に絡み合って、学校に行くエネルギーが足りなくなっている状態が不登校です。ですから、保護者の方が「全部自分のせいだ」と一人で抱え込み、ご自身を責める必要はまったくないのです。
不登校の現状:過去最多の今、「特別なこと」ではなくなっている
統計で見る不登校児童生徒数(小中学校)の推移
現在、小中学校で学校をお休みしているお子さんの数は、統計を取り始めて以来、過去最多となっています。このことからも分かるように、不登校は決して珍しいことや「特別なこと」ではなくなっています。
なぜ増えている?「学校に行かなければならない」という価値観の変化
その背景には、「学校には絶対に行かなければならない」という価値観が少しずつ変化し、「休むことも選択肢の一つ」という考え方が広がってきたことがあります。
共通の話題が難しい?情報過多社会がもたらすコミュニケーションの変化
また、今はインターネットやスマートフォンで、一人ひとりが全く違う情報に触れる時代です。昔のようにクラス全員が同じ話題で盛り上がるのが難しくなり、友達とのコミュニケーションの取りにくさを感じるお子さんが増えていることも、要因の一つと考えられています。
不登校の要因は「ひとつ」ではない。様々な要因が複雑に絡み合った結果
要因の分類:学校・家庭・本人に関わるもの
不登校の原因は、「これが原因です」と一つだけ特定できるものではありません。多くの場合、「学校生活のこと」「ご家庭のこと」「お子さん自身のこと」といった、いくつかの要因が複雑に絡み合って起こります。
学校生活での要因(例:友人関係、学習のプレッシャー、先生との関係)
例えば、学校では「お友達との関係がうまくいかない」「勉強についていくのが難しくなった」「先生との関係で悩んでいる」といったことがきっかけになる場合があります。
家庭環境での要因(※「親のせい」ではなく、環境の変化や家族の悩みなど)
また、ご家庭の要因といっても、それは「親のせい」ということではありません。お引越しによる環境の変化や、ご家族の介護問題でのお悩みごとなど、家庭内の雰囲気が影響することもあります。ライフイベントひとつだけではそれほどストレスでないことも、たくさん重なるとストレスになることは大人でも良くあることです。しかも、ライフイベントの発生は予測ができず、思わぬ時に重なることも多々あります。
お子様本人の特性や気質(例:HSC、疲れやすさ、不安の強さ)
さらに、お子さん自身がもともと持っている「疲れやすさ」「不安を感じやすい」「まわりの空気にとても敏感で繊細」「音に敏感」といった本来の気質が関係していることも少なくありません。これらの要因がいくつも重なって、学校へ行くエネルギーが尽きてしまうのです。
大人が精神的な疲れで休むのと同じ。不登校も「心身のSOS」です
大人が仕事を休む時、誰か一人のせいにしますか?
例えば、私たち大人でも、仕事のプレッシャー、職場の人間関係、ご家庭のこと、そして自分自身の体調など、様々な要因が複雑に重なって「もう心が疲れたな」と感じ、会社をお休みすることもあります。その時、「あの人のせいだ」とか「全部自分のせいだ」と、誰か一人だけを原因として責めるでしょうか。多くの場合、そうではないはずです。
お子様の不登校も同じ。目に見えない様々な要因が重なった「エネルギー切れ」のサイン
お子さんの不登校も、これとまったく同じです。学校での友人関係、勉強の悩み、先生とのこと、ご本人の疲れやすさなど、目には見えにくい沢山のことが重なり合って、学校へ行くためのエネルギーが「エネルギー切れ」を起こしてしまっている状態なのです。それぞれのイベントは小さいものなので、どうしたらよかったのかということもないところが難しいところです。
だからこそ、「誰かのせい」と考える必要はありません
これは、お子さんからの大切な「心身のSOS」のサインです。だからこそ、「誰かのせい」と考える必要はまったくありません。
「親のせい」という自責の念を手放し、お子さんのために「今できること」
まずは保護者自身の心を休ませる。自分を責めない環境づくり
「私のせいだ」とご自身を責めるお気持ちは、一度手放してみましょう。まず一番大切なのは、保護者の方自身が心を休ませることです。保護者の方が追い詰められていては、お子さんも安心できません。あなた自身がもしできるのなら、ゆっくりお休みする時間を短くても取ってみてください。
お子さんの「休みたい」という気持ちを否定せず、安全基地になる
そして、お子さんの「休みたい」という気持ちを否定せず、そのまま受け止めてあげてください。ご家庭が「ここにいても大丈夫」と思える「安全基地」になることが重要です。
家庭だけで抱え込まない。外部の専門機関(スクールカウンセラー、フリースクール等)を頼る
家庭だけで抱え込まず、スクールカウンセラーや地域の相談窓口、フリースクールなど、外部の力を頼ることも大切です。「なぜ学校に行けないのか」と原因を探すことよりも、「これからどう過ごそうか」を一緒に考えていきましょう。
まとめ:不登校は「問題」ではなく、お子さんにとって必要な「休息期間」
不登校は、決して「親のせい」ではありません。また、今や決して「特別なこと」でもありません。大人が様々な疲れやプレッシャーで仕事を休むのと同じように、お子さんも学校生活や人間関係、社会の変化など、目に見えない多くの要因が重なって「エネルギー切れ」を起こしている状態なのです。
ですから、不登校を「悪いこと」や「問題」と無理に捉える必要はありません。これは、お子さんが心と体を守るために選んだ、大切な「休息期間」です。
今は、ご家庭という安全な場所でゆっくりとエネルギーを充電する時です。保護者の方もご自身を責めず、「これからどう過ごすか」をお子さんと一緒に穏やかに考えていくことが、次の一歩につながっていきます。
不登校への理解も社会的に広がってきています。ぜひ、ゆっくりとペースを守りながら繋がりを一緒に少しずつ増やしていくことを私たちも考えられたらと思っています。
ゲムトレに五年間通われた保護者の方に書いていただいたブログ記事です。
https://note.com/tokk/n/n7e2ab5db1c9f
体験会のお申込みはこちらから!
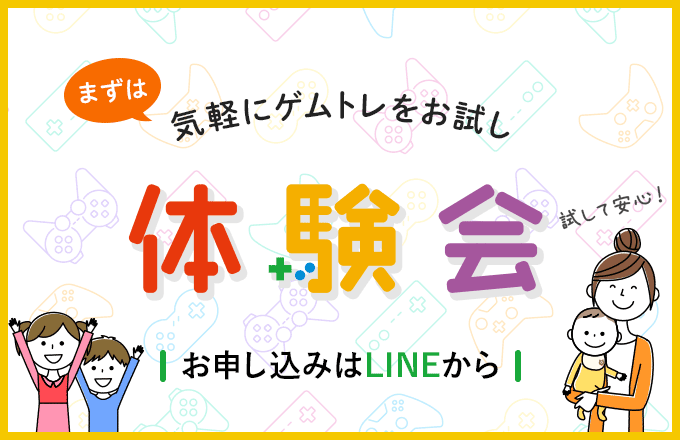
個人レッスン向けのゲムトレpersonalもご好評をいただいています。